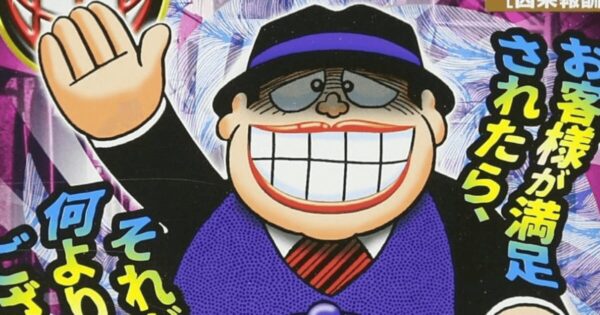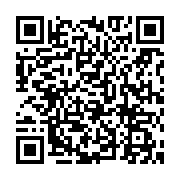TVアニメ放送開始から35年以上多くの人に愛され続けている『それいけ!アンパンマン』(以下、『アンパンマン』)。しかし、実はアニメ化には知られざる苦労と驚きのエピソードが隠されていたのです。
◆原作者の地元・高知県ではアニメ化しなかった──やなせたかし先生が「スポンサーになる!」と宣言
1988年から放送が始まったTVアニメ『アンパンマン』は、子供からの人気とは裏腹に、アニメ化の話は難航していたといいます。
2018年10月に『文春オンライン』で公開された「アンパンマン放送30周年! 「まあ1年続けば……」と言われたアニメが人気爆発したワケ」という記事によると、複数のテレビ局やアニメの制作会社が企画を出しても最終段階で頓挫するという状況が3年も続いたそうです。
ようやく企画は通ったものの、局側からはスポンサーなしの自費制作を求められるなど、前途多難なスタートでした。
しかし、放送が始まると視聴率は予想を大きく上回る7%を記録し、時には10%を超えることも。
翌1989年3月には文化庁のテレビ優秀映画に選ばれるなど、高い評価を得ました。このときに贈られた奨励金600万円により、放送枠も広がりました。
それでも原作者・やなせたかし先生の故郷である高知県ではなかなか放送されず、2013年12月出版の阿川佐和子さんの著書『阿川佐和子のこの人に会いたい9』(出版社:文春文庫)で、やなせ先生が「放送局の人に「僕の郷里でやってないのはおかしいんじゃないか」と言ったら、「どうもスポンサーが付きませんで……」って。「じゃあ、俺がスポンサーやってやる!」ってしばらくスポンサーやってたんです」と、驚きの舞台裏が明かされました。
原作者自らがスポンサーになるという異例の事態。故郷への深い愛情を感じます。
◆やなせ先生は引退するつもりだった──撤回した理由は……
生涯漫画家として現役を貫いたやなせ先生ですが、実は「引退」を考えていた時期もあったそうです。
2013年8月に『ほぼ日刊イトイ新聞』で公開された「箱入り爺さんの94年」という記事で、糸井重里さんとの対談で、やなせ先生は自身の「生前葬」の準備をしていたことを明かしています。
「みんなに告別式の文章を書いてもらってね、準備は完全にできてたんですよ」「ところが、あの大震災が起きたでしょう。これ、冗談にはならないんだよね」「こっちでほんとうに人が死んでるのに、生前葬なんてふざけたことはできないと、中止になったんです」「だから、ちょっとまた死ぬのが遅れたんだね。死ぬ準備は全部してあるんですよ。自分の位牌がもうできてるんです」と、やなせ先生は語りました。
そして、震災がきっかけで「引退しようと思っていたのを、撤回した」「そうして、東北の慰問を始めたんです」と、活動を継続する決意をしたそうです。
2012年5月に宮城県の「仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール」を訪れたときには、震災後に仙台在住の女の子から「私は怖くない。アンパンマンが助けに来てくれるから」という内容の手紙をもらったことに触れ、ファンからの手紙に励まされているとコメントしています。
◆ドキンちゃんのモデルは有名女優──しょくぱんまんと決して結ばれない理由は……
みんなの人気者ドキンちゃん。実は、彼女にはモデルとなった人物がいたのです。
1997年7月出版の『アンパンマン伝説』(出版社:フレーベル館)によると、ドキンちゃんのモデルは、1939年公開のアメリカ映画『風と共に去りぬ』のヴィヴィアン・リーさん演じる「スカーレット・オハラ」。
やなせ先生はドキンちゃんについて「ドキンちゃんは何故か僕の母親の面影があり、性格は妻に似ている」と語り、当初はばいきんまんの助太刀をするキャラクターにするつもりだったそうです。
ところが、作品を描いているうちに彼女は作者の手を離れ、「ドキンちゃんはどんどん強くなり ばいきんまんはあごで使われる」ようになり、個性的なキャラクターへと成長を遂げました。
ドキンちゃんといえば、しょくぱんまんへの一途な片想いも有名ですが、2003年11月出版の月刊誌『MOE』12月号(出版社:白泉社)のインタビューで、同作の関係者は「2人は絶対結ばれることはありません」と断言。「なぜなら片方はバイキンで片方は食品ですから」「でもかなわなくても恋をすることはある」と語っています。
結ばれなくても一途に想いを寄せるドキンちゃんの姿を、視聴者は応援したくなるのかもしれません。
◆ばいきんまんはなぜ「ハヒフヘホ」と言うのか?──実際に子供たちに聞かせた結果……
ばいきんまんが事あるごとに叫ぶ「ハ~ヒフ~ヘホ~!」。この独特な叫び声の裏には、意外な理由が隠されていました。
2005年2月出版の『人生なんて夢だけど』(出版社:フレーベル館)によると、当初は必ずしも「ハ行」に固定されておらず、まれに「パ行」や「バ行」になることもあったそうです。
しかし、子供の反応が良かったことから「ハヒフヘホ」に定着したとのこと。
ちなみに2019年1月に『J CASTニュース』に掲載された「永丘昭典監督が語る、アニメ「アンパンマン」が平成の約30年で「変わった」ことと「変わらない」こと」という記事のインタビューで、アニメの放送が進むにつれ、「ばいきんまんとかが「コノヤロー」といった乱暴な言葉を使っていた頃もありますが、そうした表現は避けるようになりました」と、言葉遣いに配慮するようになったことを明かしています。
「それは、テレビ版のメインターゲットの視聴層が未就学児だと分かったからです」「スタート当初から視聴率も予想を大きく上回るほどの人気で、作品の影響力を意識するようになり、「小学校入学前の子供が(乱暴な言葉を)真似しないように」「お父さんやお母さんが『子供が真似をしないだろうか』と心配せずに楽しめるように」と考えました」と、理由も明かしました。
──やなせたかし先生亡き後も愛され続けている『アンパンマン』。子供たちの間で高い人気を誇っていたにもかかわらず、アニメ制作にまつわる大人たちが消極的だったのは意外です。
高知県において原作者自らがスポンサーになったという驚きのエピソードなど、知られざる苦労があったからこそ、『アンパンマン』の人気は全国に広がったのかもしれません。
〈文/花束ひよこ〉
※サムネイル画像:Amazonより