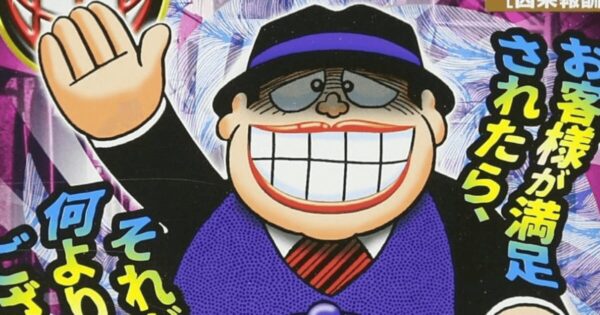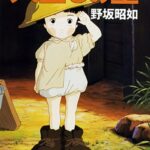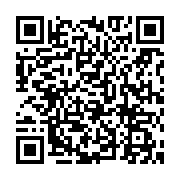昨日、8月15日に映画『火垂るの墓』が『金曜ロードショー』で放送されました。
ジブリ映画の中でも、もっとも対照的といってもいい『火垂るの墓』と『となりのトトロ』ですが、実は意外な共通点があります。あまりにも異なる世界観ゆえに気づかない点にも、2作品を比較すると驚きの事実が見えてきます。
◆2つの対照的なアニメ映画、実は2本同時上映だった
『火垂るの墓』と『となりのトトロ』は、映画が公開された当時、実は2本同時上映でした。その背景には、1984年公開の『風の谷のナウシカ』のヒット、1986年公開の『天空の城ラピュタ』の制作もひと区切り付いたことで、宮崎駿監督が長年温めていた『となりのトトロ』の制作を検討し始めたことがありました。
宮崎駿監督は『となりのトトロ』を60分の中編作品として考えていましたが、当時の映画館では単独公開は難しいという事情があり、2本立てにして上映する案が持ち上がったそうです。そこで企画に上がったのが『火垂るの墓』でした。
ところが、企画を持ち込んだ徳間書店からは「お化けに加えて墓か!」と叱責され、企画をなかなか認めてもらえませんでした。しかし、新潮社の佐藤亮一社長が徳間書店の徳間康快社長に共同プロジェクトを呼びかける電話を直接かけたことで、ようやく2本のアニメ映画の製作計画が進められることになったと、今年7月15日に『デイリー新潮』で配信された「高畑勲と宮崎駿が競い合った「お化けと墓」 映画「火垂るの墓」ついに配信開始 1988年波乱の公開前を振り返る」という、当時の映画製作担当者へのインタビュー記事の中で明かされています。
ようやく公開にこぎつけた2作品は、多くの劇場で『となりのトトロ』、『火垂るの墓』の順で上映されました。楽しいアニメを見ようと映画館を訪れた多くの観客は、『トトロ』が終わり、『火垂るの墓』が始まるや衝撃を受けます。涙が止まらない、茫然自失で席から立ち上がれない観客もいたと、綿矢りさ氏は自身の著書『かわいそうだね?』(出版:文藝春秋 2013年)の中で、当時の映画館の様子を語っています。
今やジブリを代表する作品となった2タイトルが公開された1988年は、まだまだアニメ映画作品の黎明期でした。本来であれば、これだけ世界観の違う作品を同時上映するのはスタジオジブリとしても不本意だったでしょう。当時の日本において、アニメ映画の製作企画がいかに大変だったかがうかがえるエピソードだといえます。
◆サツキと節子は「同級生」 戦時中と戦後であまりに違う世界観……
作中の設定の中にも、驚きの事実があります。『となりのトトロ』のヒロイン・草壁サツキと、『火垂るの墓』の妹・節子は、実は「同級生」です。
同じくジブリのアニメ映画『コクリコ坂から』のパンフレットによると、宮崎駿監督の想定では『となりのトトロ』の時代は1953年で、作中でサツキは12歳の設定でした。
一方、第二次世界大戦が終戦した1945年を描いた『火垂るの墓』に登場する節子は4歳の設定です。つまり、より過去の時代を舞台とする『火垂るの墓』の節子が仮にその後も生きていたなら、『トトロ』の時代である1953年には12歳となり、サツキとはほぼ同級生となります。
病気がちな母親の心配はあるものの、優しい父親と家族3人で楽しく暮らす草壁家を描いた『トトロ』を見ていると、当時その後に上映された『火垂るの墓』のストーリーは、胸をえぐられるほど辛く、清太と節子が不憫でなりません。
作中で14歳の青年だった清太は、生きていれば終戦後は日本の復興を担う若い力となったかもしれません。節子もサツキと同じように同級生たちと学校に通い、楽しい学生生活が待っていたことでしょう。
戦争によって家族や家、さらに命すら失った戦災孤児の顛末を描いた『火垂るの墓』。一方、『となりのトトロ』からは、戦争を生き延びた家族がその後の日本を強く生きる「希望」や「夢」といったものを感じます。
一見まったく違う世界観の2作品ですが、「戦争について深く知り、考える」という観点では、実はセットで見るべき作品なのかもしれません。
◆実は清太たちのほうが裕福だった?
疎開先の叔母の家を出てからは、その日食べるものにも困る生活を送っていた清太と節子ですが、実は裕福な家庭に生まれた兄妹でした。
作中で、2人の父は海軍大尉であることが描かれていますが、当時の軍上官ともなればかなりの高待遇だったと推測できます。裏付けとして、清太が銀行に母の残した貯金を下ろしにいくシーンがありますが、残高は7,000円だったと明かされています。
1945年当時の貨幣価値に換算すると、一説によれば現代の200万円にも相当する額だといわれています。
一方、サツキとメイの父・タツオは、1988年に徳間書店より出版された『ロマンアルバム・エクストラ69 となりのトトロ』によると、東京の大学で非常勤講師として考古学を教える傍ら、生活費を稼ぐため翻訳の仕事もしていたとされています。
当時の非常勤講師の収入は、かなりの低水準だったといわれており、事実タツオは副業もしています。また、妻の靖子は結核を患って七国山病院に入院しており、治療費の負担も考えると、決して裕福な家庭ではありませんでした。
そんな2つの家族ですが、清太と節子は大金を手にしたにもかかわらず栄養状態が悪かったことなどから命を落とし、貧しいはずの草壁一家は笑顔にあふれ、つつましくも毎日を楽しく生きていました。
『となりのトトロ』には、「トトロ」や「ネコバス」といった空想上の生き物が登場し、サツキやメイを助けてくれますが、草壁家に直接的な「富」をもたらしてくれたわけではありません。
2つの作品を比較すると、あらためて戦時中に親を失い「生きる術」を持たない子供たちが、人知れず命を落としていった悲惨な情景が見えてきます。
──商業的な事情により、くしくも同時上映となった『火垂るの墓』『となりのトトロ』には、「近しい時代設定」という奇妙な一致がありました。その点を加味したうえで、あらためて2作品を見てみると、昔から同作を知っている視聴者も、今まで感じることのなかった「戦中、戦後の光と影」が見えてくるかもしれません。
〈文/lite4s〉
《lite4s》
Webライター。『まいじつ』でエンタメ記事、『Selectra(セレクトラ)』にてサスペンス映画、韓国映画などの紹介記事の執筆経験を経て、現在は1980~90年代の少年漫画黄金期のタイトルを中心に、名作からニッチ作品まで深く考察するライター業に専念。 ホラー、サスペンス映画鑑賞が趣味であり、感動ものよりバッドエンド作品を好む。ブロガー、個人投資家としても活動中。
※サムネイル画像:Amazonより 『「アメリカひじき・火垂るの墓」(出版社:新潮社)』