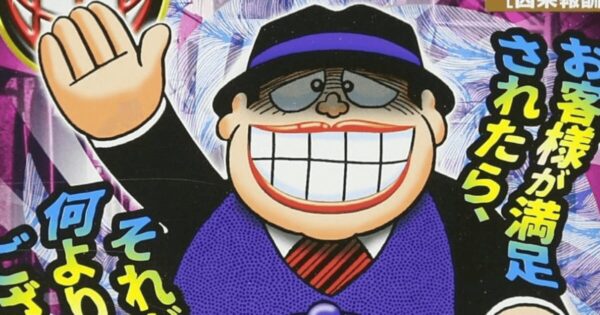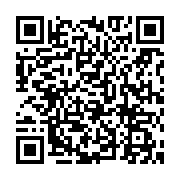<この記事にはアニメ・原作漫画『鬼滅の刃』のネタバレが登場します。ご注意ください。>
きょう7月18日から全国で公開が始まった『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。舞台は鬼の本拠地「無限城」となり、数多くの鬼たちが登場しています。そんな鬼たちの中には、鬼殺隊士同様「痣」のような「紋様」が描かれている者も……。
◆鬼の「紋様」と鬼殺隊の「痣」の共通点
外見に痣のような「紋様」が浮かんでいる鬼たちを振り返ってみると、最初に登場したのは元十二鬼月で下弦の数字を剥奪された響凱でした。続いて登場した下弦の伍・累や下弦の壱・魘夢、そして上弦の鬼たちにも等しく「紋様」が描かれています。
唯一、上弦の肆・半天狗だけは外見を見ただけでは「紋様」らしきものが見当たりません。しかし、半天狗は目の周りから額にかけて変色しており、それが「痣」のようにも受け取れます。つまり、総じてみるとほぼほぼ十二鬼月クラスの強い鬼にしか「紋様」が描かれていないのです。
一方で一部の鬼殺隊士に発現した「痣」も、強者にしか現れていません。なぜなら、作中に登場した「痣者」は竈門炭治郎を除くと全員が柱でした。
また第128話で、始まりの剣士たちも全員「痣」が発現していたことが産屋敷あまねによって明かされています。始まりの剣士の時代といえば、鬼舞辻無惨を生涯で唯一単身で追い詰めた継国縁壱のいた時代です。まず間違いなく強い剣士が集まっていたと推察できるでしょう。
このことから、鬼の「紋様」も鬼殺隊の「痣」も強者にのみ現れるという共通点があることが分かります。そして強者とは、肉体の限界を凌駕した者だと考えられます。十二鬼月はもちろん人間を凌駕した肉体を持っていますし、鬼殺隊で「痣」を発現した者の肉体も常軌を逸しています。作中の描写を見ても、身体能力が飛躍的に上がるだけでなく、受けた傷が普通の人間では考えられない速さで回復していました。
そう考えると、「痣」も鬼の「紋様」も、肉体の限界を超えた「極致」を表すものだと考えられるのではないでしょうか。これを裏付けるように第99話では縁壱も「道を極めた者が辿り着く場所はいつも同じだ」と言っています。
◆「紋様」と「痣」の決定的な違いとは?
しかし『鬼滅の刃公式ファンブック 鬼殺隊見聞録・弐』(出版社:集英社)では、容姿である鬼の「紋様」についての解説は一切ありません。そんな中で、鬼側の容姿で明確に「痣」と表記されている人物が二人います。それが黒死牟と竈門禰豆子……。
余談ですが、猗窩座の紋様は幾何学的な「入れ墨」と紹介されています。これはもちろん彼の過去が大きく関わっています。そして、黒死牟の「痣」についても彼の人間時代が大きく関わっており、鬼になってから後天的に発現したものではありません。つまり、人間時代の名残が鬼となったあとも身体に残っているのです。
ここで注目したいのは、黒死牟たち以外のほかの鬼の紋様が「痣」と表記されていなかった点です。裏を返すと、吾峠呼世晴先生の中で二つは区別して考えていたと捉えられないでしょうか。結論からいうと、その違いこそ「人間性」の有無だと考えられます。ここでいう人間性とは、有限の「命」を含めています。
「痣者」は肉体の限界を凌駕して人智を超えた力を発揮できますが、肉体を酷使している分、当然デメリットもあります。それが第170話で黒死牟によって明かされた通り、発現した者は例外を除いて短命に終わるという「寿命の前借り」です。
しかし、鬼たちは永遠に近い寿命とすぐに再生する肉体を持っているので、自らの「命」すら顧みていません。つまり、常に肉体を酷使しても問題ないのです。その証拠に、基本的に鬼殺隊士の「痣」は現れたり消えたりしますが、鬼の「紋様」は擬態などで消さない限り、常に身体に刻まれたままとなっています。ここが決定的な違いといえるでしょう。要するに、己の「命」を含めて大切にする「人間性」すらなくした者は、消えない「紋様」が身体に刻まれるとも捉えられるのです。
ちなみに、縁壱は生まれたときから常時「痣」が発現していますが、これは黒死牟のセリフを借りるなら「この世の理の外側」にいるからだと解釈できます。その分縁壱は、他者が幸福であることを強く願い、日々の小さな物事に喜びを感じる、誰よりも尊い「人間性」を持った人物として描かれているのです。
◆なぜ禰豆子に「痣」が出現したのか?
公式ファンブックでは、禰豆子が鬼の力を引き出した際に身体に現れた紋様も「痣」と表記されていました。彼女はなぜ鬼となってから「痣」を発現させられたのでしょうか? その理由は、大きく三つ考えられます。
まず一つが「痣」が出たときの禰豆子の「強さ」になります。第83話で、堕姫が驚愕している通り、このときの禰豆子は上弦を上回る再生速度を手にしています。さらに単独で堕姫を圧倒していた描写から、少なくとも十二鬼月クラスの強さだったと考えられるでしょう。
続いて二つ目の理由は「人間性」を保っていたことだと考えられます。禰豆子は鬼となったあとも人を食べず、鱗滝によって「人間は家族」だと刷り込まれていました。これは鬼としてかなり異質な存在でした。だからこそ、例外として「痣」が発現したとも考えられます。
そして、三つ目の理由が「炭治郎の存在」です。第128話であまねが「痣の者が一人現れると共鳴するように周りの者たちにも痣が現れる」と語っていました。作中で最初に痣が発現したのは炭治郎で、その炭治郎のそばにいつも一緒にいたのが禰豆子なのです。
さらに注目したいのが、禰豆子が何かしらに覚醒するきっかけは、必ずといっていいほど炭治郎が危機に陥っているときなのです。
たとえば、第40話で血鬼術「爆血」をはじめて発動させたとき、炭治郎は絶体絶命の状況でした。さらに第127話で太陽を克服する前、炭治郎は禰豆子の命と鬼殺隊の使命の狭間で揺らいでいた極限の状況だったのです。
このことからも炭治郎が常に禰豆子を守ってきたように、禰豆子もまた最愛の家族である炭治郎を守り続けてきたことが分かるでしょう。まさにそれは鬼であるにもかかわらず、誰かの「命」を守る「人間性」があったことにもつながってきます。
こうしたさまざまな理由が重なり、禰豆子は「痣」を発現できたのではないでしょうか。そして禰豆子の身体に現れた「痣」は、奇しくも鬼が嫌う「藤」の葉のような紋様でした。この「藤」の花言葉には「決して離れない」という意味があります。もしかしたら炭治郎との絆や想いも、禰豆子が「痣」を発現させた理由の一つかもしれません。
──原作では鬼の「紋様」と「痣」の関係について最後まで明かされませんでした。しかし、そこには我々読者を楽しませる余韻が残されているのです。こういった細かい部分に改めて注目してみるのも、作品の深みをより体感できるのではないでしょうか。
〈文/fuku_yoshi〉
※サムネイル画像:Amazonより 『Blu-ray「鬼滅の刃 」遊郭編 第4巻【完全生産限定版】』
※禰豆子の「禰」は「ネ+爾」が正しい表記となります。
※鬼舞辻の「辻」は「一点しんにょう」が正しい表記となります。