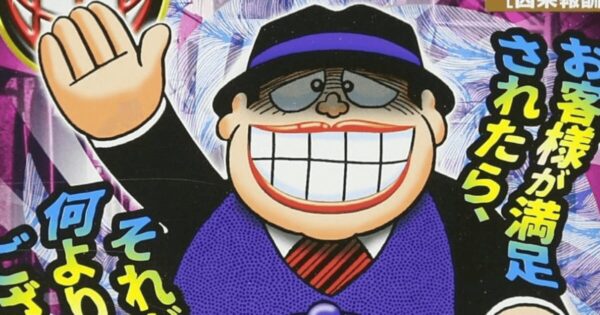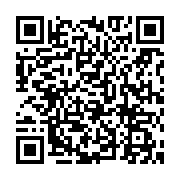『薬屋のひとりごと』の舞台は、架空の中華風帝国・茘(リー)ですが、この国には皇后がいません。茘は実在した中国の唐の時代をモデルにしていますが、唐は世界三大美女の一人・楊貴妃がいた時代でもあります。
ここでは主に、書籍『中国の歴史 A History of China 06 絢爛たる世界帝国 隋唐時代』(出版社:講談社)を参考に、なぜ『薬屋のひとりごと』に皇后がいないのか紐解いていきます。
◆唐の時代には皇后がいなくても妃嬪がいれば問題なかった
『薬屋のひとりごと』の後宮には2000人の女性がいますが、唐の後宮は、その20倍、もっとも多いときには4万人の女性がいたそうです。
後宮のトップに君臨するのは皇后です。皇后は皇帝の唯一の正妻(内外で公認された妻)として、後宮の女性をまとめるリーダーでした。
TVアニメ『薬屋のひとりごと』では、この皇后の座が空席となっています。「誰が皇后になるの?」と気になりながらも、原作のネタバレを読まないように皇后となる人物を予想している人もいるのではないでしょうか。
現実の唐の皇帝には皇后がいないことが多く、その理由としては、まだ皇后の制度や後宮の体制が完全に整っていなかったことが挙げられます。そのため、身分の低い女性でも皇帝に愛されて妃嬪となったり、皇后になるチャンスがあったりしたのです。
しかしながら、家柄を重んじる男性官僚は、皇帝に寵愛される家柄の良くない妃嬪が皇后となり、政治権力を握ることを恐れていました。彼らは、皇族またはそれに近い家柄の女性でない妃嬪が皇后になることを、基本的に認めていなかったのです。
形だけの皇后の下には、多くの妃嬪、皇帝の妾がいました。もっとも丁重に扱われたのは、皇室の親戚や権力者、名門貴族の令嬢です。唐は漢民族の国家ではなく北方遊牧民の国家だったため、高貴な血筋を持つ漢民族の女性を後宮へ招き、家同士のつながりを作ることで政治基盤を固めることに力を入れていたのです。
家柄の良い家の娘は選ばれる形で後宮へ入りましたが、多くは妃嬪の身の回りの世話や、後宮の仕事をこなす宮女で終わってしまったといいます。
一般市民や猫猫を育てた三姫のような妓女が後宮の貢物として入ることもありました。また、罪人の娘が宮廷の官婢(奴隷)として所有され、そこから後宮の妃嬪となる非常にまれなケースもあったようです。
ちなみに唐では、女性は13歳前後で後宮に入るのが一般的でした。『薬屋のひとりごと』に登場する里樹妃や安氏皇太后が13歳以下で先帝の妃になったのは、作中だけでなく、唐でも異例中の異例だったことがよく分かります。
妃嬪の中で皇后に継ぐ地位にいたのは四夫人と呼ばれる存在だけです。貴妃、淑妃、徳妃、賢妃の座にそれぞれ一人ずつ女性が選ばれます。
そしてもっとも人数が多いのが宮女。玉葉妃や梨花妃といった妃嬪の日常を支える侍女が宮女にあたります。その下には、後宮での仕事を任されている猫猫や小蘭(作中の下女)のような存在がいました。
◆唐の後宮の女性たちは、ほかの中国王朝朝の女性と比べて自由だった?
『薬屋のひとりごと』で桜蘭妃の前任である阿多妃は男装の麗人として描かれていますが、唐の時代には阿多妃のように男装をする女性が多かったそうです。
この時代には、馬に乗ってボールを追いかけるゲームが流行しており、男性のみならず女性の間でも行われ、後宮の女性もこのスポーツを楽しんだのだとか。
何より唐は儒教思想の影響が弱かったため、女性は男性と対等に接することができ、笑う、泣く、怒る、嫉妬するといった感情を素直に表現できたおおらかな時代だったといいます。その点は『薬屋のひとりごと』のストーリーと似ているといえるでしょう。
──7月4日に最終回を迎えたTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期。アニメ放送終了後、続編の製作が発表された本作ですが、はたして第3期では皇后は登場するのでしょうか? こういった点も、TVアニメ『薬屋のひとりごと』の注目すべき部分といえるかもしれません。
〈文/国木ちさと 編集/乙矢礼司〉
※サムネイル画像:https://kusuriyanohitorigoto.jp/news/588/より 『薬屋のひとりごと 第2期キービジュアル ©日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会』
アニメ「薬屋のひとりごと」公式サイト
©日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会