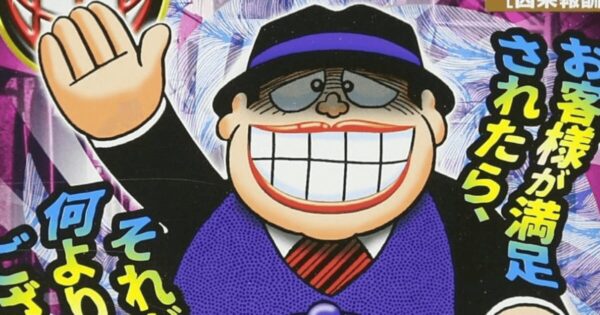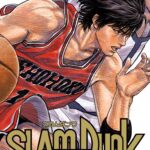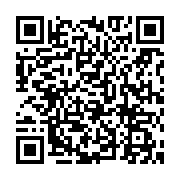山王戦の土壇場、流川の脳裏に浮かんだのは、なぜ絶対王者・沢北ではなく、陵南のエース・仙道だったのか──。多くの読者が抱くこの疑問こそ、仙道という男の本当の凄さと、流川の“覚醒”の秘密を解き明かすカギとなります。そしてその答えは、二人の激闘の中にこそ、隠されているのです。
◆「まだ仙道の方が上」──流川が初めて“自分以上の存在”と認めた男
流川が仙道を意識し始めたのは、ある決定的な一言がきっかけでした。
インターハイ県予選で海南との激闘を終えたあと、安西先生から告げられた「君はまだ仙道君におよばない」という言葉です。
誰よりも高いプライドを持つ流川にとって、安西先生の指摘は自身の心に深く突き刺さるものでした。この瞬間から、仙道はたんなるライバルではなく、流川が超えるべき明確な「尺度」となったといえます。
もちろん、仙道の実力は練習試合で初めて相まみえたときから肌で感じていました。1on1のスキルでは一歩も引かず、互角の勝負を繰り広げた流川。しかし、試合の最後に勝負を決めたのは、土壇場で驚異的な集中力と冷静さを発揮した仙道でした。このとき、流川は仙道が持つスコアラーとしての能力以上の、得体のしれない「格」のようなものを感じ取っていたはずです。
“格の違い”が決定的に浮き彫りになったのが、インターハイ出場をかけた県予選決勝リーグでの再戦です。この試合で流川は驚異的な得点能力を発揮しますが、仙道は冷静にチーム全体を動かす「ゲームメイク」で応戦しました。
ファウルトラブルに陥った魚住をなだめ、精神的にムラのある福田を巧みに活かす。味方の弱点すらも計算に入れ、チームの勝利という一点のために自らの能力を使う仙道の姿。自分の得点でチームを勝たせることしか考えていなかった当時の流川にとって、まったく理解の及ばないバスケットボールだったといえるでしょう。
つまり、流川にとって仙道とは、1on1のスキルだけでは測れない、試合そのものを支配する「自分以上の存在」だったといえます。尊敬とは違う、むしろ認めたくないほどの強烈な印象として、彼の心に深く刻み込まれました。だからこそ、自身の限界に直面したとき、無意識にその姿を思い浮かべてしまったのではないでしょうか。
◆1on1の終焉──沢北が突き付けた「個の壁」と仙道の「ゲーム支配術」
そして舞台は、山王戦へ。ここで流川は、自身のバスケ人生を根底から覆す衝撃を経験します。日本最高の選手、沢北との対決です。
高校入学以来、1on1では負けないという絶対的な自信を持っていた流川。しかし、そのプライドは沢北の前に打ち砕かれます。得意なはずのドライブは止められ、逆に沢北の個人技に翻弄される。流川が初めて味わう「個の力」による完全な敗北でした。自分の得意な土俵でまったく歯が立たないという現実は、流川に「自分一人の力では勝てない」という事実を突きつけたといえます。
このとき、流川の脳裏をよぎった「仙道なら…どうする」という心の声。「仙道なら沢北に1-on-1で勝てるか?」という意味ではありません。自問の本質は、「仙道なら、どうにもならないこの状況をどう打開し、チームを勝利に導くのか?」という、より次元の高いものだったはずです。
ここで思い出されるのが、県予選での仙道の姿です。彼は個人技に固執せず、魚住や福田といった仲間を生かすパスでゲームをコントロールしていました。それは、チームメイトを駒として使い、勝利への道筋を描く、司令塔そのものでした。流川は、自分に欠けていたその「勝利への道筋を描く力」を、無意識に仙道の姿に求めたのではないでしょうか。
沢北という絶対的な「個」の壁にぶつかったからこそ、流川は「個」を超えるバスケの必要性に気づきました。山王戦での自問は、スコアラーからゲームの支配者へと進化するために、避けては通れない心の叫びだったといえるでしょう。
◆「パス」という名の革命──仙道が教えた“勝利への視野”とエースの条件
仙道の姿を思い浮かべた流川が、自ら導き出した答え。それは「パス」という、あまりにシンプルでありながら、彼のバスケ人生において革命的ともいえる選択でした。
これまで自分一人で道をこじ開けてきた流川が、初めて仲間を生かすプレーに目覚めたのです。
絶対的なディフェンダーである沢北を「囮」として使い、赤木へ、そして三井へとアシストを決める。これらのプレーは、もはやたんなる戦術変更ではありません。相手のエースを利用して味方を輝かせるという、まさに仙道が得意とするゲームメイクの発想そのものでした。
そして物語は、伝説のクライマックスを迎えます。残り時間わずか、シュート体勢に入った流川。誰もが彼自身が打つと確信したその瞬間、ボールはノーマークの桜木へと渡りました。流川が、最も認めたくないであろうライバルを、チームの勝利のために「信頼」して託したパス。彼が己のエゴを完全に乗り越え、真のエースへと覚醒した瞬間といえるでしょう。
一連のプレーを通じて、流川は仙道から学んだ「視野の広さ」を完全に自分のものにしたといえます。そして、「仲間を信頼する」という一点において、彼は仙道すらも超える領域へと足を踏み入れたのかもしれません。仙道は流川を成長させた「見えざる師」だったのです。
仙道の本当の凄さとは、彼の卓越したスキル以上に、ライバルの内に秘められた可能性の扉を開かせた点にあるのではないでしょうか。流川が仙道を思い出したのは、彼が「個」の勝利を超える「チームの勝利」を知り、本物のエースになるための、最後の試練であり最大のヒントだったといえるでしょう。
──流川が山王戦の土壇場で仙道を思い出した理由。それは、彼が1on1という「点」の勝負から、試合全体を支配する「面」の勝負へと進化するために、仙道が唯一の道標となる存在だったからといえるでしょう。
最高のライバルの存在こそが己を成長させるという物語の核心を、仙道という男は体現していたのではないでしょうか。
〈文/凪富駿〉
※サムネイル画像:Amazonより 『「SLAM DUNK 新装再編版」第19巻(出版社:集英社)』