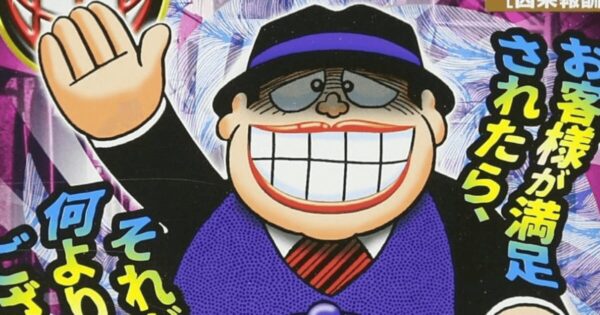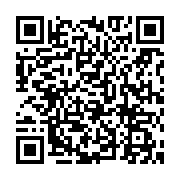読者の誰もが笑ったであろう、桜木花道の「フンフンディフェンス」は、なぜ赤木や魚住からいとも簡単にボールを奪えたのか、その理由は意外なところにあります。原作でたった二度しか描かれなかった、この幻の技にこそ、花道の「天才」たる理由と、常識では測れない守備能力の本質が隠されていると考えられます。
◆誕生! フンフンディフェンス ── 素人の“思い込み”が生んだ奇策
フンフンディフェンス誕生の瞬間は、花道がバスケ部に入部する以前に訪れます。バスケットボールのルールも、守備のやり方さえも知らない花道。彼はただ純粋に、「相手からボールを奪う」という一点のみに集中していました。
0対9と一方的に実力の差を見せられ、攻撃すらできない状況。ここで花道は、誰に教わるでもなく、自らの本能に従って動きます。腕を目一杯伸ばし、相手を威嚇するように「フンフンフン」と繰り返し、あらゆるコースを塞ぐ技。常識を知らないからこそ生まれた、完全に自己流の守備体勢こそが「フンフンディフェンス」誕生の瞬間です。
ではなぜ、この技が絶対的な格上である赤木に通用したのでしょうか。答えは、技術的な優劣ではなかったのかもしれません。当時の赤木は、花道を「ズブの素人」と完全に侮り、ボールを奪われる可能性など微塵も考えていなかったといえるでしょう。
フンフンディフェンスの最初の成功は、相手のその「油断」と「意表」を完璧に突いた、心理的な奇襲だったといえます。9点差をつけ、勝利を確信していた赤木は、まさか素人がここから本気でボールを奪いに来るとは夢にも思わなかったハズです。赤木の思考の隙を、素人の怖いもの知らずの精神が打ち破ったと考えられます。
つまり、最初のフンフンディフェンスは、技術ではなく「心理戦」での勝利であり、バスケの常識の外にいた花道の本能的な動きが、赤木の心の隙を突いた、まさに「奇跡のプレー」だったといえるでしょう。
◆常識を破壊する“予測不能な動き” ── 魚住が感じた本当の脅威
赤木との対決で見せたフンフンディフェンス。その幻の技が再び火を噴いたのが、陵南との練習試合でした。
負傷した赤木に代わり、背番号10・センターとしてコートに立った花道。対峙するのは、陵南の主将であり「ボス猿」の異名を持つ、魚住です。赤木戦での成功体験から、花道はフンフンディフェンスを「自分だけの必殺技」として確信し、大舞台でためらうことなく繰り出しました。この揺るぎない「自信」が、無意識のうちにプレーのするどさを増していたのかもしれません。
ではなぜ、あの魚住が、いとも簡単にボールを奪われたのでしょうか。ここにも、赤木戦と同様の「油断」が見え隠れします。湘北の絶対的支柱である赤木が下がり、代わりに出てきたのが「赤頭のド素人」。魚住の心に、一瞬の緩みが生まれたとしても不思議はありません。
しかし、陵南戦での成功の理由はそれだけではなかったのかもしれません。赤木のような正統派のセンターの動きを予測していた魚住にとって、意味不明な動きをしながらあらゆるコースを塞いでくる花道は、まさに「未知との遭遇」だったハズです。バスケットボールの常識的な動きを予測すればするほど、その思考の枠の外から来る花道の動きに対応できない。経験豊富な選手ほど陥りやすい、思考の罠だったといえるでしょう。
つまり、陵南戦での成功は、赤木戦から続く「相手の油断」と、バスケットボールの常識からかけ離れた「予測不能な動き」という、二つの要素が合わさった結果といえます。このプレーは、経験豊富な選手ほど常識外れの動きに対応するのが難しく、思考が停止してしまうという、フンフンディフェンスの恐るべき本質なのかもしれません。
◆天才を“最強”に変える驚異の肉体 ── 消えたフンフンディフェンスの「その後」
赤木、そして魚住に通用したフンフンディフェンス。しかし、この技が明確に描かれたのは陵南との練習試合が最後でした。なぜ、花道は自らの必殺技を封印したのでしょうか。
その理由は、皮肉にも花道がバスケ選手として「成長」したからでしょう。基礎練習や試合での実戦を経て、花道は正しい守備の姿勢や駆け引きを学び始めます。バスケの常識を身につけたことで、無意識に「あんな動きは無謀だ」と、自分に歯止めがかかるようになったのかもしれません。フンフンディフェンスは、花道が「完全な素人」だったからこそできた、一瞬の閃光のような技だったといえるでしょう。
しかし、技そのものは消えても、魂は花道の守備の根源として受け継がれていきました。フンフンディフェンスの本質とは、相手の意表を突く「予測不能な動き」と、それを可能にする「驚異的な身体能力」といえます。あの奇妙な動きは、並の身体ではすぐに体勢を崩し反則となる危険な賭けでした。花道の人間離れした瞬発力があったからこそ、あの奇策は成立していたと考えられます。
豊玉戦での南への執拗なマークや、山王戦で沢北を追い詰めた鬼気迫る守備。これらのプレーには、最後まで相手に食らいつく執念や、常識外の動きで相手のリズムを崩す、フンフンディフェンスの魂が見え隠れします。技の形は消えても、成功体験として体に染みついた「本能」は、彼の守備を支え続けたといえるでしょう。
フンフンディフェンスは、花道がバスケの常識を学ぶ過程で姿を消した「幻の技」でした。しかし、その根底にあった「予測不能性」と「身体能力」という二つの要素こそが桜木花道の守備の本質であり、彼の成長の基盤となった最強の武器だったのかもしれません。
──なぜ花道のフンフンディフェンスは2回しか登場しなかったのか。それは、相手の油断と意表を突く、素人だからこそできた心理的な奇襲であり、花道がバスケの常識を学ぶにつれて姿を消した、「幻の技」だったからではないでしょうか。
しかし、その根底にあった「予測不能な動き」と「驚異的な身体能力」は、彼の成長の基盤となりました。未熟さすらも武器に変える花道の可能性は、常識に囚われず、自分の強みを信じ抜くことの大切さを教えてくれるのかもしれません。
〈文/凪富駿〉
※サムネイル画像:『「SLAM DUNK」第2巻(出版社:集英社)』